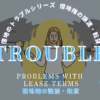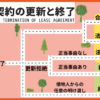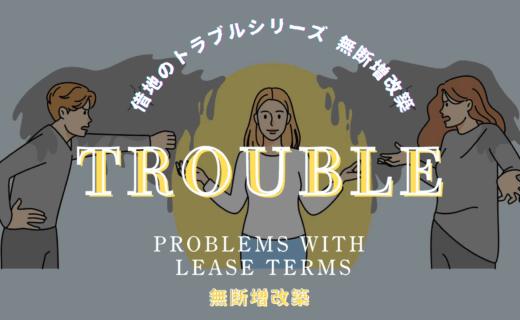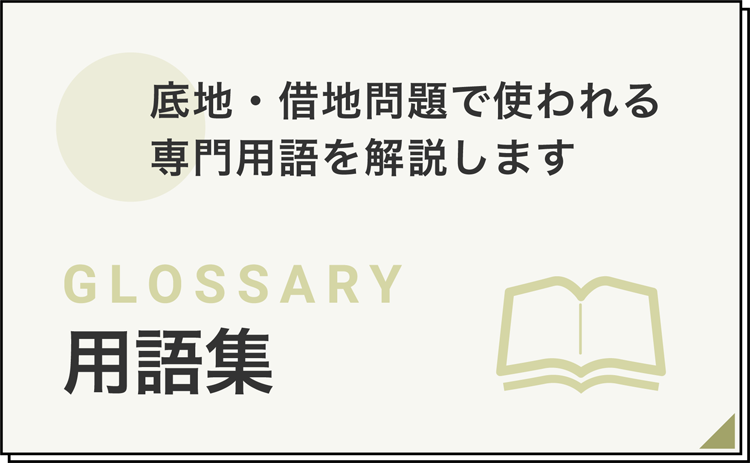借地権のトラブルシリーズ、借地権の譲渡および転貸についてです。
底地や借地に担保(抵当権)の設定を行う場合があります。その際無事返済等が終わればよいのですが、返済等が滞り、抵当権を実行された場合には借地についてはどうなるのでしょうか。
それについて今回解説していきます。
1.底地に担保権が設定された場合
土地を借地として借りたところ、抵当権者から底地の担保権を実行するとされた場合どうなるのでしょうか。
- 借地の賃借→抵当権の設定の場合
これについて結論から申し上げると、借地の賃借と抵当権の設定の時期によります。借地の賃借のあとに、抵当権が設定登記がなされた場合は、借地の賃借権が優先されるため借地人は明け渡しの必要はありません。
- 抵当権の設定→借地の賃借の場合
一方で、借地の賃借の前に抵当権の登記が行われている場合は、抵当権が優先されるため明け渡しをしなければなりません。ただし、6ヶ月間の明け渡し猶予というものがあります。
以前は「短期賃貸借制度」というものがあり、5年間の猶予(5年間は抵当権者/競落人に対抗できる)がありました。
ただ、この「短期賃貸借制度」は現在廃止されており、抵当権者に対抗するには賃貸借の登記前に抵当権を設定しているすべての抵当権者に同意を得ることが必要となります。これを「同意の登記」といいます。この場合単に抵当権者全員の同意だけでなく下記の要件を満たす必要があります。
- 抵当権者全員の同意
- 賃借権の登記
- 同意の登記
この3つを満たすことで対抗できるようになります。
「1抵当権者全員の同意」はもちろんですが、「2賃借権の登記」は、建物の登記ではなく、賃借権の登記をしていることを示しています。つまり、借地権が第三者に対抗するためには借地権上の建物の登記をしていることで対抗できましたが、今回の場合はこれでは不十分で「賃借権の登記」が必要になります。次に「1抵当権者全員の同意」を得ただけではなく、この同意されたことについてを登記する必要があります。この3つについてを満たすことで先の抵当権者についても借地権を対抗できるようになります。
2.建物の担保権の実行
こちらは、借地人が借地上の建物を担保として抵当権を設定する場合のお話です。
借地上の賃借人が建てた建物については借地人に所有権がありますのでこれを担保にすること自体は可能です。ただし、建物の所有権の移転が発生する譲渡担保については建物が立っている借地についても移動(譲渡)するため地主の承諾が必要となります。
一般的には抵当権者である債権者(銀行等)は万が一に際して担保権の実行をすることを想定して融資を行う場合には事前に担保にいれる借地の「地主の承諾書」を求めます。これは担保権の実行をすると、借地の所有者が新しい所有者に移動するため後々のトラブルを避けるためのものです。
もし、担保権が実施され新しい建物の所有者となった人は借地人になれるのでしょうか。もし借地について地主の承諾を得られない場合には裁判所に地主の承諾にかわる許可について裁判の申立を行い、借地人となることが可能です。これについては多くの場合は許可が出るようです。
また補足ですが、地上権は担保にできますが、賃借権は原則として担保にできません。地上権は物権であり、土地に対する直接的な権利であるため、抵当権を設定して担保とすることが可能です。一方、賃借権は債権であり、土地所有者との契約に基づく権利であるため、原則として抵当権を設定できません。代わりに賃借権の場合借地上の建物に抵当権を設定することでこれに代えています。
担保権については別の記事でも解説しております。参考にしていただければと存じます。